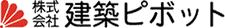| 会社名 |
株式会社福本構造設計 |
|---|---|
| 設立 | 1976年 | 所在地 | 北海道札幌市 |
| 主な作品 |
札幌南高等学校 札幌市立芸術の森小学校 小樽市道営住宅であえーる稲北団地 日新団地市営住宅1号棟 北海道名寄高等学校(増築工事) 義務教育学校 湧別町立ゆうべつ学園(増築工事) |

「DRA-CAD」はいつからお使いですか?

陶山様
1992年に入社した時、すでに会社ではMS-DOS版の「DRA-CAD2」を使用していました。
学校ではCADの授業はなかったため、入社後に「DRA-CAD」でリストを描いたのが初めてのCAD経験でした。
マニュアルを読み、基本的な使い方を先輩から少し教えてもらった後、すぐに使えるようになったことを覚えています。
最初に「DRA-CAD」を使用された感想・思い出があれば教えてください。

「DRA-CAD」は手描きと同じ感覚で作図できるのもあって、使いやすいCADだったという印象です。
以前、MSDOS版の「JW_CAD」が建築知識の付録についてきた時に試してみたことがありましたが、
「DRA-CAD」の方が使い勝手が良かったこともあり、以来ずっと「DRA-CAD」を使っています。
入社当時、20代の社員はCADを使っていましたが、それより上の世代は手書きでした。 一般図は手書きで、リストをCADで描いていましたが、徐々に一般図もCADで作成するようになりました。 当時の「DRA-CAD」では描ける線分の本数が限られていたので、設定をいろいろと工夫して線本数を増やしていました。 ただ、実際の図面では増やしても足りないことがあり、当初は苦労した記憶があります。
入社当時、20代の社員はCADを使っていましたが、それより上の世代は手書きでした。 一般図は手書きで、リストをCADで描いていましたが、徐々に一般図もCADで作成するようになりました。 当時の「DRA-CAD」では描ける線分の本数が限られていたので、設定をいろいろと工夫して線本数を増やしていました。 ただ、実際の図面では増やしても足りないことがあり、当初は苦労した記憶があります。
昔からパソコンが得意だと伺いましたが、プログラミングもされているのでしょうか?

今はあまりしていませんが、以前は作図を効率化するためにいくつかのコマンドを自作していました。
例えば、「DRA-CAD18」に標準搭載された「連続等間隔複写」コマンドは、正確な作図を作るために私が出したアイディアです。
屋根の受け材や間柱を指定した等間隔で割り付ける際に便利で、審査機関からの「図面と計算が一致しない」という指摘を
防ぐことができるようになりました。
構造設計が主な業務ですか?

はい、基本的には構造設計を行いながら、「DRA-CAD」で図面を作成しています。
耐震診断や耐力調査の仕事も多く、まずは構造計算を行い、その結果に基づいて軸組図や詳細図を「DRA-CAD」で作成しています。
今後、「DRA-CAD」に期待する改善点はありますか?

他社とのデータのやり取りは非常にスムーズで、変換効率も素晴らしいです。
構造図面を描く上では、十分な機能のあるソフトだと思います。
一点気になる点としては、最近はレイヤ設定コマンドのダイアログ表示が少し遅いと感じます。
わずかな時間ですが、「DRA-CAD」を素早く操作できるだけにその違いを感じます。
環境設定コマンドでは、マウスの 両ボタン押し(「左右同時クリック」)に機能を割り当てた場合、コンマ何秒か遅くなることがあります。
これは、左ボタンを押した後に右ボタンも押されているかを確認するための仕様ですが、
「左右同時クリック」 を使われない場合は、「なし」にするなど、設定を変更されることをお勧めします。

DRA-CADを活用したプロジェクトの中で、特に思い入れのあるプロジェクトを教えてください。

札幌南高等学校のプロジェクトです。屋上に鉄骨フレームで楕円形のドームを設計しましたが、
当時の「MS-DOS版DRA-CAD」では線本数が足りず、どうやって図面を描くか悩んだ経験があります。
構造計算は構造システムの「FAP-3」を使用しました。


最近では、ニセコのひらふで、海外の設計者によるプロジェクトの構造設計の依頼を受けました。
国内では考えられないような大スパンを150mmほどの壁で支え、全面を開口にするというデザインでしたが、
積雪を考慮しなくても構造的に無理がありましたので、修正提案を行いました。
海外の設計は日本の常識とは異なる部分があり、興味深い経験でした。
「最後に」
今回のインタビューでは、福本構造設計様の「DRA-CAD」に対する長年の信頼と実際の業務での活用例をお聞きしました。
特に、「連続等間隔複写」コマンドの誕生秘話は非常に印象深く、
建築ピボットとしてもユーザーの皆様の声をもとに機能開発が進められていることを改めて実感しました。
これからも福本構造設計様のようなプロフェッショナルの現場で、「DRA-CAD」がさらに貢献できるよう製品の向上に努めてまいります。
貴重なお時間をありがとうございました。