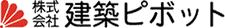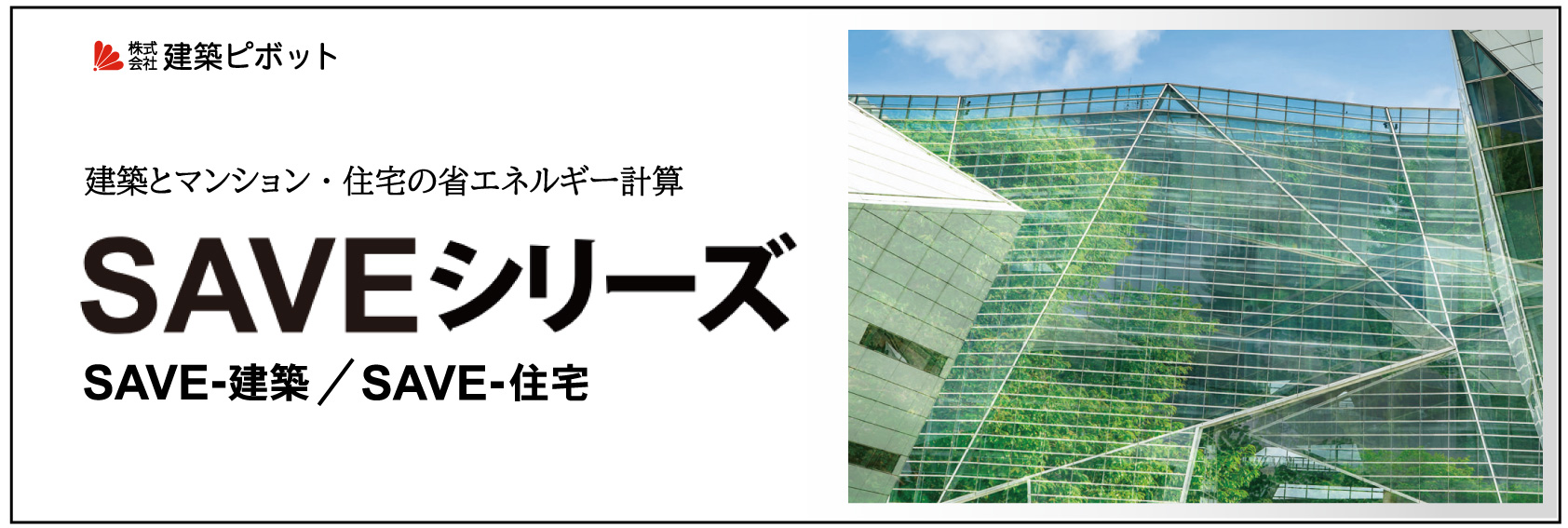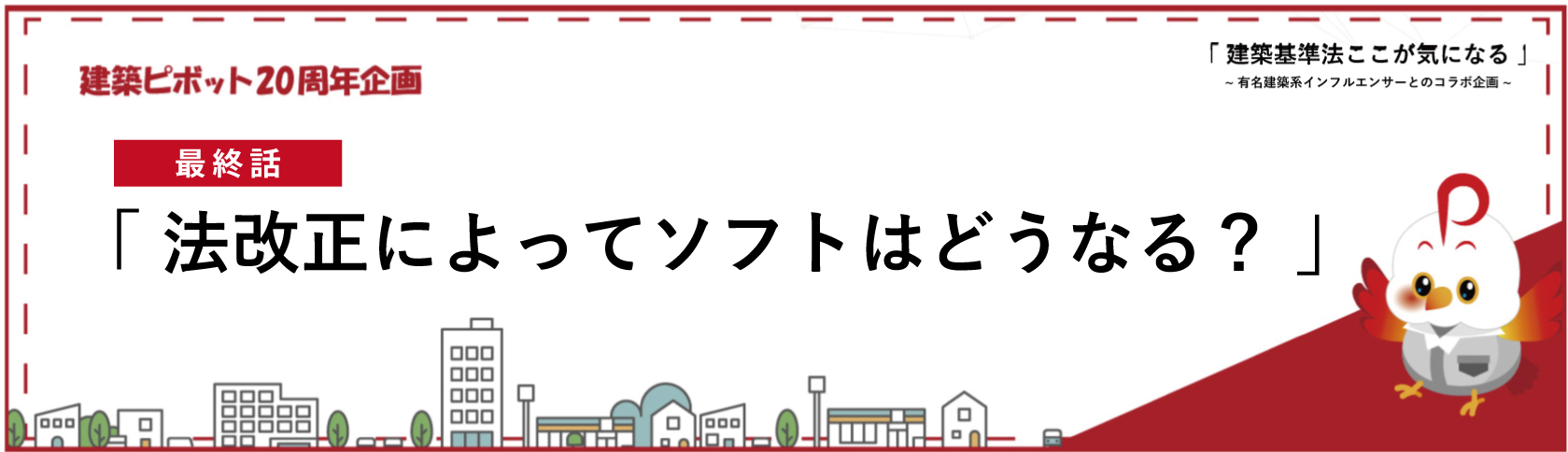
「今回の法改正によってソフトはどうなるのか」
ー今回の法改正がソフト会社にとって追い風になるのではないかという意見がありますが、そぞろさんはどうお考えですか?
そぞろ氏 そうですね。今回の改正は確かにソフト会社にとって大きなチャンスなんじゃないかと客観的に思っています。 特に構造計算ソフトの分野では、各メーカーがこぞってアピールしていますよね。今回の改正によって木造2階建ての建築確認審査が厳格化され、従来は必要とされなかった構造計算が求められるケースが増えました。 これにより、構造計算ソフトのニーズは確実に高まるでしょう。
一方、省エネソフトの分野はどうなんでしょうか。 省エネ計算についても適合義務の対象が拡大しており、手作業では対応しきれないレベルになってきていると思いますが、 まだ手作業で行っている方は多いのでしょうか?
ピボット(原) 現状では、設計者が省エネ計算を外注するケースが多いと思います。弊社の省エネ計算ソフトを活用し、省エネ計算を請け負っているユーザー様も多数いらっしゃいます。外注する理由としては、やはり計算の煩雑さでしょうか。 設計事務所が自前で計算を行うには、手間が増えてしまうのは事実なので専門家に依頼したほうが確実という判断なのでしょうかね。
ー過去に審査機関でお仕事をされていたとお聞きしましたが、審査機関側が導入しているソフトウェアなどはあるのでしょうか?
そぞろ氏 少なくとも私が働いていたときは、省エネ計算はほとんど手計算で行われていました。 国が提供しているエクセルシートもあるのですが、結局手入力が必要な部分が多く、計算の効率性や正確性には課題がありました。熱損失係数(Q値)や外皮平均熱貫流率(UA値)の算出において、開口部や外壁の詳細な入力など項目が多いです。 もし省エネ計算が自動化されれば、申請する側も審査する側も負担が大幅に軽減されると思います。
ピボット(谷道) また、AIの技術発展とは別に、「うちのソフトだけで申請書類がすべて揃います」というソリューションもあれば、設計者にとっても大きなメリットになりますよね。 もし木造2階建て専用で、意匠設計・構造計算・省エネ計算が一体化したソフトがあれば、設計業務の負担は大幅に軽減されるはずです。 確認申請の電子化と組み合わせることで、申請業務の迅速化にもつながるのではないでしょうか。
そぞろ氏 確かに、それが実現すれば業界にとって大きな変化になりますね。先ほどのAI技術の発展より現実的な話になります。
ピボット(谷道) 特に中小の設計事務所にとっては、専門的な計算業務を外注せずに済むため、業務の幅が広がりますね。 また、BIMとの連携を強化すれば、設計データをそのまま確認申請に活用できるため、二重入力の手間が省け、人的ミスも減らせるはずです。
ピボット(原) 弊社のソフトウェアでも、ある程度それに近いことは可能です。 たとえば、構造計算を「HOUSE-ST1」で行い、 そのデータを「SAVE-建築」や「HOUSE-省エネ」などの計算ソフトに連携することで、 省エネ適合判定に必要な書類を自動生成することができます。さらに、今後はBIMデータから直接計算ソフトに情報を連携する仕組みを強化すれば、よりスムーズなワークフローが実現できると思います。
そぞろ氏 「ワンクリックで申請書類が完成する」といったレベルの統合システムが実現すれば、設計業界に革命が起きるかもしれませんね。 AIやクラウド技術の発展とともに、今後の可能性がますます広がっていくのが楽しみです。
ーそうですね。ソフトウェアを提供する側として、今後ともみなさまの業務をサポートできるように取り組んでいきたいと思います。そぞろさん、本日は貴重なお時間をありがとうございました。
「まとめ」
今回の20周年企画では、建築系インフルエンサー「そぞろ氏」と、現状の建築基準法の問題点や、今回の法改正が建築業界やソフトウェアに与える影響について対談する機会を持ちました。 実際にソフトウェアの設計や審査に携わる立場だからこそ、制度の課題や現場での運用とのギャップに気づくことが多く、具体的な意見が交わされました。 建築ピボットでは、今後も最新の業界動向や実務に役立つ情報を積極的に発信し、設計・計算業務の効率化をサポートしてまいります。引き続き、建築ピボットの取り組みにご注目ください!
省エネルギー計算を行うなら