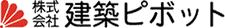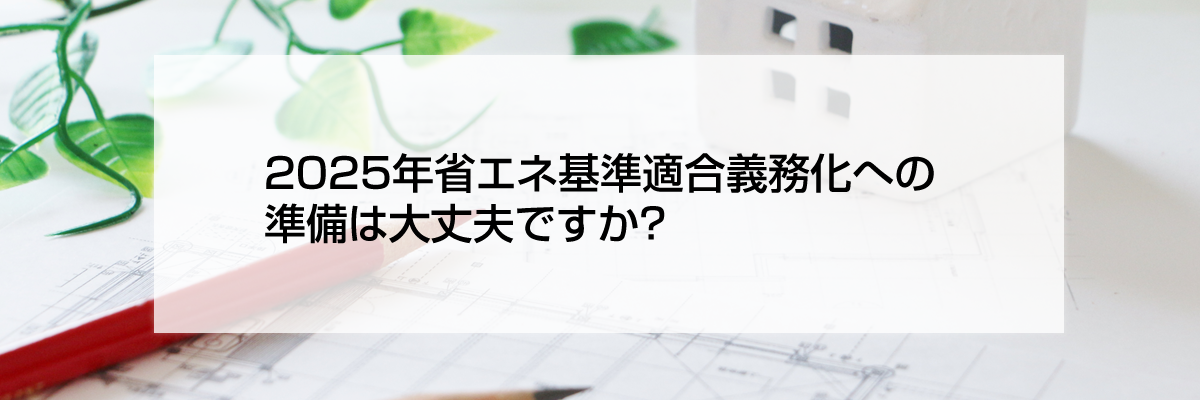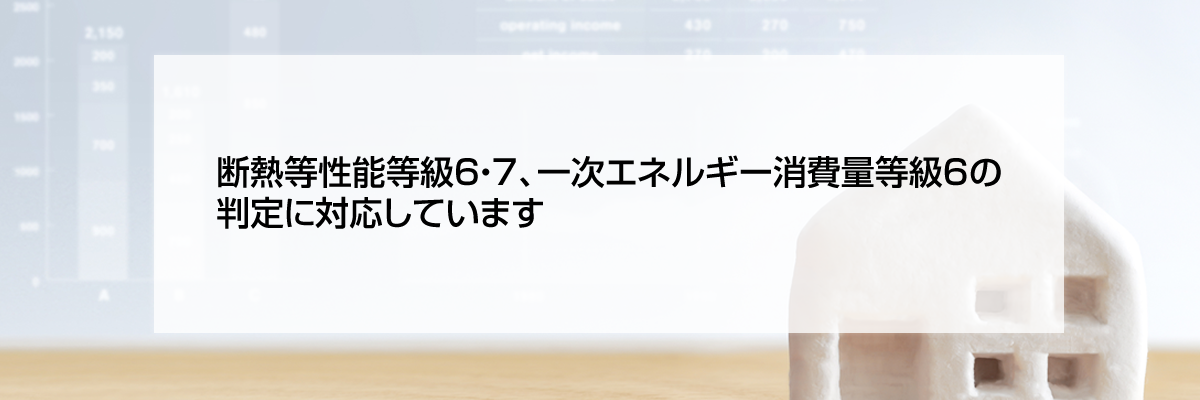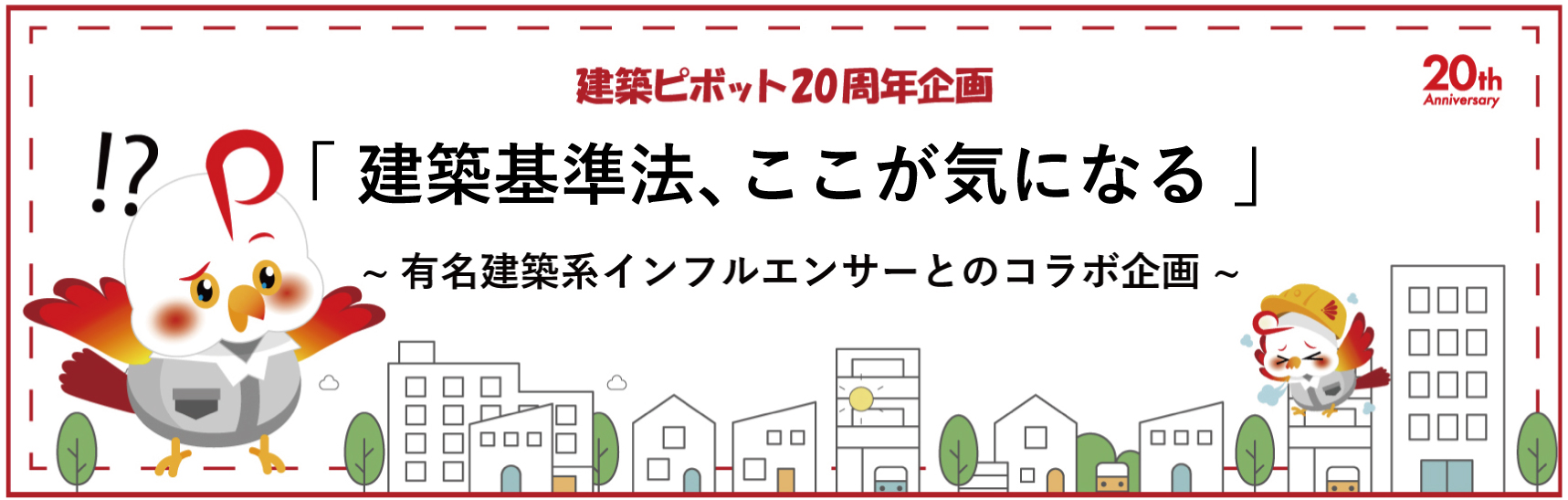
建築系インフルエンサー・そぞろ氏と対談!建築基準法の気になるポイントを語る
2024年某月、元審査機関で活躍されていた建築系インフルエンサーのそぞろさんと確認申請ソフトウェアの開発を手掛ける建築ピボットが、 建築法規に関する素朴な疑問や業界の現状について語り合う特別対談を実施。 対談では、法改正に伴う実務の課題や審査の裏側でのエピソードなど、多岐にわたる話題が議論されています。 ぜひ、お仕事の合間のリフレッシュにご一読いただければ幸いです。

そぞろ氏
ブログ 「建築基準法とらのまき。」 の運営者。指定確認検査機関にて5000件以上の確認申請を審査した経験をもとに、 難解な建築基準法を「分かりやすく」解説し、積極的な情報発信を行っている。 著書である 「用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規」 の増補改訂版が、 2025年の法改正に対応し、新たに告示構造の早見表などを追加して、2025年3月29日に発売予定。
「木造2階建ての確認申請が必須に!建築業界に迫る法改正の波」
ー本日はお忙しい中お越しいただき、ありがとうございます。オンラインで何度かお打ち合わせさせていただきましたが、 こうして直接お会いできるのは初めてですね。 限られたお時間ではありますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします!
そぞろ氏 こちらこそ本日はお会いできて嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
ーまずは最近の建築の法改正から触れていきたいと思います。2025年4月から木造2階建ての確認申請が必要になりますよね。この改正は私たち建築業界にどのような影響を与えるとお考えですか?
そぞろ氏 そうですね。これまでは木造2階建ては確認申請の特例が適用されることが多かったですが、2025年4月からはそれが使えなくなります。結果として全ての木造2階建て住宅において確認申請が義務付けられることになります。
ーこれは業界全体にとって大きな変化となりますね。
そぞろ氏 はい、建築士や設計事務所にとってはもちろん、審査機関に関しても大きな影響があるとおもいます。審査機関の方々は、さまざまな苦労をされているのではないでしょうか。 やはり申請のほとんどが木造2階建てだったんです。木造2階建てでしたら構造計算とか採光などの審査は必要なく、接道や建蔽容積などを審査すれば確認済証を交付できていたんです。 今までの特例に頼っていた部分を、今後は特例なしに確認をしなくてはならなくなります。
ー確認事項の対象となる数が一気に増えそうです。
そぞろ氏 はい、構造図や地盤調査、あとは壁量計算も、、、審査機関も業務は増えますが、申請者側の手間も増えることとなります。

「国が推奨する木造建築。建築法改正の現状と課題」
ーなるほど。今回は大きな法改正になりそうですね。近年の省エネの法改正など、建築法が年々厳しくなっている印象がありますが、災害など何か最近の環境の変化などのきっかけがあるのでしょうか?
そぞろ氏 実は、ここ数年で起きているのはほとんど緩和なんです。特に木造の大規模建築物を建てやすくするためにずっと緩和が進んでいます。ただ、その内容が非常に難解で、審査機関の人も設計者も理解しきれていない状況なんですよ。
ー厳しくなっているというよりむしろ緩和されているのでしょうか。
そぞろ氏 はい、そうなんです。低炭素の対策として国はとりあえずできる手段だけは用意してるんだと思います。ただ、その手段が実際に現場で活かせるかと言われたら全然できていません。
ピボット(江田) 実際に令和3年に、避難安全検証法にも新たな算定方法「煙高さ判定法(ルートB2)」が追加されましたね。
ールートB2はまだ解説書も出ていないと聞きますが、審査機関の方はそのような法改正があった際はどのようにチェックしているのでしょうか。
そぞろ氏 その都度法文を読んで、勉強して手探りで確認しています。すごく大変です。ルートB2も内装制限の適用除外をしやすくするための制度で、結局は木(もく)の活用を推しているんですよね。そのために最近は色々と法改正が行われているのですが、でも、これも複雑で難しくて。
ーでも、木を伐採するとなると、私みたいな素人からすれば逆に環境破壊に繋がるんじゃないかとも思ってしまいます。
ピボット(原) いえ、そうではないんです。日本には伐採しなくちゃいけない木がいっぱいあります。スギの木とか。毎年花粉で凄いことになりますよね。 あと、密集した木をきちんと間引かないと良いものが育たなくなるので、伐採しないと新しい木が育たない問題もあります。日本には伐採すべき木がたくさん残っているんです。海外から木を輸入するくらいなら日本のものを使って欲しいという政府の方針だと思います。
ーそういうことなんですね。私、いつも矛盾してるなと思っていたんです。木を伐採するのにそれがなぜ環境保全のための施策になっているのか。
ピボット(原) 木材は再生可能な資源なので、その木を上手く活用して需要が増えれば、永久に供給されるようになります。そうすると木を作り続けられる循環づくりの仕組みができるんですよ。
ーでも、木造建築って耐火性や耐久性が心配ですよね。
ピボット(谷道) その点は確かに議論が多いです。特に高層階とかの建物を木で作るのは、、、
そぞろ氏 最近では木造でも耐火性能を持たせた建物が出てきていますが、木とRC(鉄筋コンクリート)を同等に扱うのはどうしても気になります。
ピボット(谷道) 確かに木造は火にさえ当たらなければ丈夫ですけど、火がついたら耐久力がどうなるかが心配ですよね。実験では一定の耐火時間が証明されていても、施工の問題や、経年による劣化の可能性もあります。
そぞろ氏 そうですね。実際に最近、とある木造の保育園で火災が起きて、準耐火建築物として設計されていたのにほとんど燃え尽きてしまいました。
そぞろ氏 最近では木造でも耐火性能を持たせた建物が出てきていますが、RC(鉄筋コンクリート)と同じような耐火性を持たせるには難しい部分があります。施工面でも、石膏ボードを厚くしなければならないなど、大変な作業が必要です。耐火にしようとすると施工現場の負担も大きいです。 国が推しているのは結局そういう燃えしろ設計っていう木造現し(あらわし)のもので、それができるように色々整理をしてと聞きますが、結局あの保育園みたいな燃え方をしちゃうと、、、 法令集も毎年どんどん分厚くなっていて国としては色々と対応策を提供しているつもりなんだと思いますが、実務では使えるものが少ないんです。
ピボット(原) 結局法改正が現場のニーズに合っていなかったり意味が見出せないものだと現場では導入が進まないことが多いですよ。あまり複雑になりすぎずに安全が保てることを第一に法を作って欲しいですね。
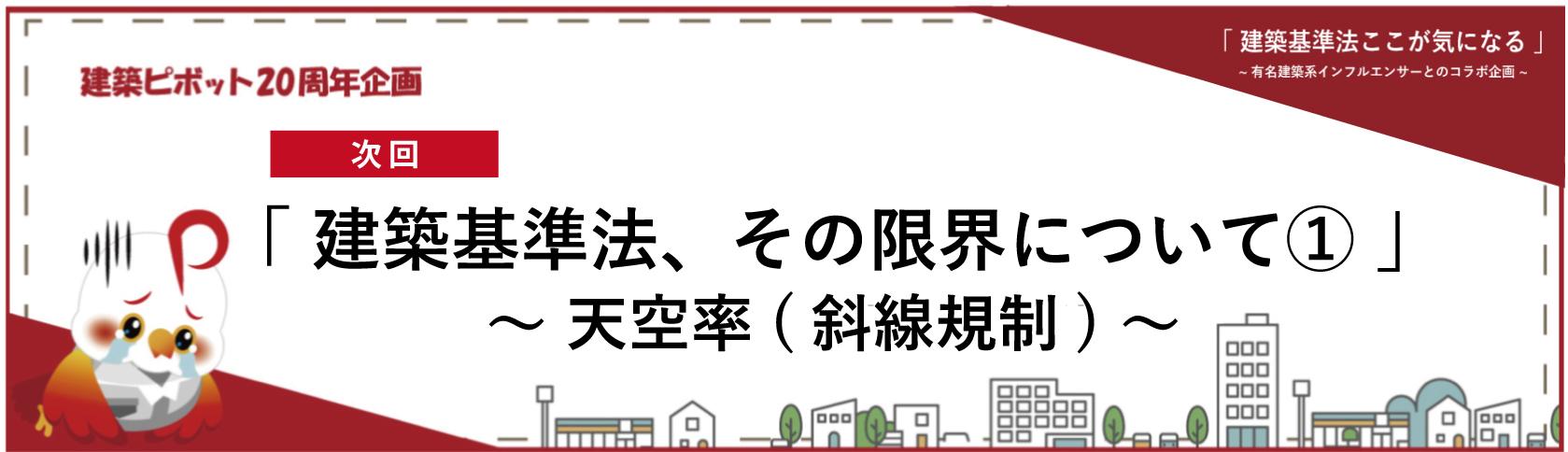
省エネの法改正について